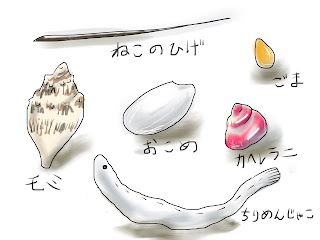パラワン島 フィリピン
 |
パラワン島

BEAD ART25掲載
|
CNN トラベルやニューヨークタイムズ等の海外メディアで理想的な旅行先として話題のパ
ラワン島は、フィリピンの西にある細長い島だ。なかでもエル・ニドは最も有名なリゾー
ト地だが、最近は観光地化が進みクオリティーが下がりつつあるといった話も聞く。私た
ち夫婦は静かなリゾートが好みなのでガイドブックに載っていない、ある隠れ家リゾート
に滞在した。
 |
| リゾートホテルのアウトリガーで探検 |
 |
| 誰もいないビーチに上陸 |
 |
| 誰もいないビーチ |
美しい海にかこまれたパラワン島では南洋真珠を養殖していて、観光客のお土産として人気だ。真珠は島の一番大きな町で空港のあるプエルト・プリンセサのマーケットなどで買うことができ、観光客の多くはここで真珠を買ってゆく。しかし気を付けなければいけないのは、ここで売っている真珠のほとんどは中国産の淡水真珠で、パラワン島の真珠はほんのごく一部でしかない。そして驚くことに、店によっては店員が産地や淡水真珠、海水真珠の違いすら分からないことがある。
 |
| ホテルのスタッフに教えてもらった信頼できる店のパラワン産真珠 |
 |
| 大粒ゴールド南洋真珠(パラワン産) |
 |
| わりとしっかりした店でもこんな感じ |
きちんとした店ではパラワン島産の真珠を取り扱っているが、当然ながら質の良いものは高価だ。大粒のパラワン島産真珠は一粒 2,000 円~60,000 円くらいとピンキリで、日本の真珠同様に形、色、傷の有無、巻き、照り、などにより価格は上下する。私はキリの方を買った。最近欧米からの観光客に真珠とマクラメやレザーなどとの組み合わせが人気で、レザーを通すために直径 5mmくらいの大きな穴があけてあるものもあった。12mm以上の大粒南洋真珠だからこそできるデザインだ。

プエルトプリンセサ近辺のMCAマーケット内
ほとんどが中国産淡水真珠
大粒のバロック淡水真珠500円くらい
|
|
MCA Market Mall は空港に近く、真珠や工芸品などのお土産を買うのにとても便利だ。空港
から歩いても行けるが、その日は雨だったので、空港でお客をおろしたばかりのトライシ
クル(原付にサイドカーを取り付けたタクシー)の兄さんをつかまえて「マーケットまで
往復 100 ペソ(およそ 200 円)払うから、買い物が終わるまで待っていてくれる?」と聞
いたらとっても嬉しそう。相場の 5 倍くらいだったようだ。
 |
| トライシクルのお兄さん |
日本では真珠というとホワイトからピンク系がポピュラーだが、フィリピンではゴールド
カラーが人気だ。私もこの島に滞在して分かったが、フィリピン人の小麦色の肌にはゴー
ルドカラーがよく映える。そして毎日ビーチであそんで、すっかり日焼けしてしまった私
には白よりゴールドのほうがしっくりくる。
 |
パラワン産の大粒南洋真珠で作ったネックレスとブレスレット
|
 |
フィリピンのリゾート地で大量発生中の
男子おだんごヘア、「マン・バン」(man bun)。
|